 072-800-1522
072-800-1522着手金
コラム詳細
目次
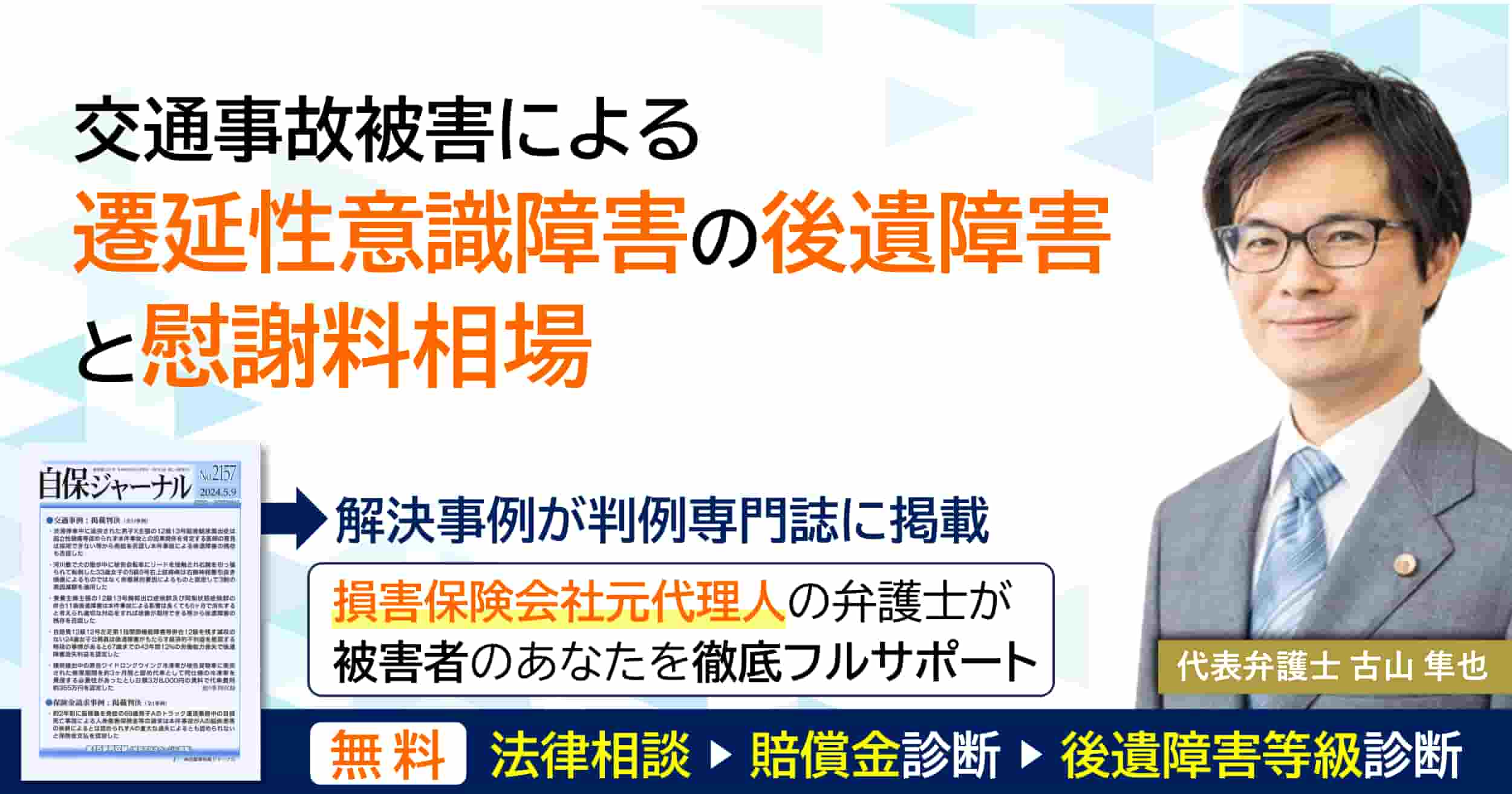
交通事故によって遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)を負ってしまった場合、その後遺障害等級や慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。
この記事では、遷延性意識障害の診断・症状から等級認定の流れ、加害者へ請求できる賠償金や弁護士に依頼するメリットまで、ポイントを整理してご紹介します。
深刻な脳損傷を受けると意識が戻らない状態が長期にわたって続く可能性があり、被害者やその家族には大きな心身の負担となります。
特に遷延性意識障害は医療費や介護費が高額になりやすく、正しい知識をもって適切な補償を得ることがとても重要です。
本記事を通じて、遷延性意識障害の概要と後遺障害認定のポイントを整理し、交通事故による被害で加害者に請求可能な賠償金や、弁護士に相談することで得られるメリットもあわせて確認しましょう。
まずは遷延性意識障害の基本的な症状や診断方法を把握し、どのような状態なのか理解しましょう。
遷延性意識障害とは、脳に重度の損傷を負った結果として意識レベルが深刻に低下し、長期間にわたり自力で意思疎通や身体の動きがほとんどできない植物状態を指します。
交通事故などによる強い衝撃を頭部に受けることで脳が広範囲にダメージを受けると、この状態に陥ることがあります。
加害者の過失が原因であれば、被害者および家族への生活面・金銭面の影響は計り知れません。
この段階では、自力歩行や自力摂食がほぼ不可能なため、医療機関や介護施設でのケアが欠かせません。
また、患者本人が言葉を発しにくいだけでなく、外界への反応がきわめて限定的になる場合もあります。
こうした症状が3ヶ月以上継続すると、日本脳神経外科学会の基準などで遷延性意識障害に該当する可能性が高まります。
遷延性意識障害の定義には明確な基準が存在し、診断には専門的な検査が必要です。
状態を正しく把握するためにも、医療の専門家による神経学的診断と継続的観察が欠かせません。
正確な診断を受けることで、今後の介護方針や補償のための手続きにおいても極めて重要な意味を持ちます。
なお、遷延性意識障害と似た症状に「脳死」があります。
その違いは次の通りです。
参照 遷延性意識障害と脳死の違い
| 遷延性意識障害 | 脳死 | |
|---|---|---|
| 脳の機能障害の範囲 | 主に大脳半球の機能に障害がありますが、脳幹の機能は保たれています。 | 脳全体(大脳、小脳、脳幹)の機能が不可逆的に失われています。 |
| 生命維持機能 | ・自発呼吸が可能で、人工呼吸器なしで生存できます。 ・自律神経反射や運動反射は維持されています。 |
・自発呼吸ができず、人工呼吸器が必要です。 ・すべての脳幹反射が消失しています。 |
| 回復の可能性 | 回復の可能性が完全には否定されません。 | ・回復の可能性は全くありません。 |
| 法的・倫理的位置づけ | 生存している状態とみなされます。 | 日本では、臓器提供を前提とした場合に限り、法的に人の死とみなされます。 |
遷延性意識障害の大きな原因としては、交通事故による頭部への強い衝撃が挙げられます。
高速度での追突などで頭を強く打つことで外傷を受け、脳に深刻な損傷を負うケースが多く見られます。
また、その結果として意識が長期間回復せず、自力で身体を動かしたり会話をしたりできない植物状態に近い状態になってしまうことが少なくありません。
主な症状としては、外部刺激に対する反応の著しい低下や、適切な意思表示の欠如などが見られます。
特に、自力での摂食が不可能なため、経管栄養や点滴による栄養管理が必要となるケースが多く、排泄も自分でコントロールできないことが一般的です。
さらに、身体の動きにも重度の制限があるため、関節の拘縮や床ずれを防ぐための定期的なケアが不可欠になります。
これらの症状が続くことで、患者自身だけでなく家族にも大きな負担がかかります。
回復の見込みが不透明であるため、精神的ストレスに加えて経済的負担や精神的な疲労も増大しやすいと言えます。
だからこそ、原因となる事故状況を正しく把握し、加害者に対して適切な賠償額を求めるための準備が必要といえます。
遷延性意識障害の診断は、医師による検査と評価によりおこないます。
前述した「参照 日本脳神経外科学会「遷延性意識障害の定義」に基づく6つの症状を3か月以上観察します。
JCS(Japan Coma Scale)やGCS(Glasgow Coma Scale)を用いた意識レベルの評価方法があります。
参照 JCS(Japan Coma Scale)の診断方法
① 患者の意識レベルをJCSの10段階(0から300)で評価します。
点数が高いほど状態が悪くなります。
②評価は主に以下の3つの大分類に基づいて行われます。
I. 覚醒している(1桁の点数)
II. 刺激に応じて一時的に覚醒する(2桁の点数)
III. 刺激しても覚醒しない(3桁の点数)
参照 GCS(Glasgow Coma Scale)の診断方法
GCSは3つの要素で意識レベルと意識内容を別々に評価します。
これらの合計点(3~15点)で意識レベルを評価します。
点数が低いほど意識障害が重度であることを示します。
たとえば、GCS 7点以下の患者は、死亡または遷延性意識障害(植物状態)になる可能性が高いとされています。
① E(eye opening・開眼機能):1~4点
② V(verbal response・言語機能):1~5点
③ M(motor response・運動機能):1~6点
・MRI(磁気共鳴画像法)やCT(コンピュータ断層撮影)による脳の構造的評価
・fMRI(機能的MRI)による脳活動の評価
・PET(陽電子放射断層撮影)やSPECT(単一光子放射断層撮影)による脳機能の評価
・脳波検査(EEG):脳の電気的活動の評価
・定量的脳波(qEEG):自動化された脳波特性の分析
・事象関連電位(ERP):認知機能の評価
上記のような検査などを通して脳の活動状態を詳しく調べます。
具体的には、脳波検査やCT・MRIなどの画像診断を活用し、脳のどの部位に損傷があるのか、どれほど重篤なダメージを受けているかを総合的に評価します。
また、一定期間観察を行い、患者が外部刺激にどの程度反応できるかも確認します。
これらの診断過程では、患者が発するわずかな反応や、家族とのコミュニケーションを試みる様子なども重要な判断材料となります。
しかし、診断には長期間を要することが多く、その間にリハビリや介護の体制をどのように整えるか、家族には多岐にわたる判断が迫られるでしょう。
医師によって遷延性意識障害の診断が下されると、後遺障害の認定手続きや損害賠償請求のための準備が必要となります。
適切な賠償金獲得のためには、症状の正確な把握と専門的知見に基づく判断がなければ、適切な補償を得るのは難しくなるため、担当医や医療機関と密に連携しながら進めることが大切です。
遷延性意識障害の診断を受けた時点で、早めに弁護士に相談をしておくと良いでしょう。
残念ながら遷延性意識障害を根本的に治療する有効な方法は確立されていません。
そのため、リハビリやケアの側面から考えられるアプローチも合わせて知っておきましょう。
参照 遷延性意識障害に対する実験的治療法
遷延性意識障害に対する実験的治療法として、以下のような神経刺激療法があります。
これは、脳や神経系に電気的または磁気的刺激を与えることで意識の回復を試みる実験的治療法です。
脊髄後索電気刺激法(DCS)/脳深部刺激療法(DBS)/迷走神経刺激療法(VNS)/正中神経刺激法(MNS)など
遷延性意識障害では、患者が寝たきりに近い状態であるため、日々の看護や介護がとても重要になります。
特に、関節拘縮を防ぐためのリハビリテーションや、排泄ケアや床ずれ(褥瘡)を防ぐための体位変換などの身体ケア、さらに栄養管理(経管栄養や静脈栄養)などを行う際の清潔管理は感染症予防(肺炎、尿路感染症など)のうえで欠かせません。
これらの対応を継続的に行うことで、患者の合併症リスクを下げることが可能です。
これは、遷延性意識障害のある方は、平均余命よりも短い期間で亡くなるケースが多いため、回復可能性の可能性は低いものの、合併症などのリスクを予防することに焦点を当てた治療に重点を置かれることがあります。
そのため、遷延性意識障害は医療的な治療というよりも、むしろケアとリハビリテーション支援が中心的な役割を果たします。
脳の回復を促進するための取り組みとしては、刺激療法や音楽療法などが試みられることもありますが、その効果は患者ごとに大きく異なります。
長期にわたるケアが必要なため、家族のみで看護を続けるのは難しく、専門施設における支援や在宅介護サービスの利用を視野に入れることも検討されます。
また、ご家族の方に向けた精神的なサポートが必要となります。
遷延性意識障害の場合、明確な回復の見通しを示すのが難しく、治療やリハビリへの取り組みが長期化しがちです。
さまざまな支援制度を確認し、医療社会福祉士や弁護士(将来的な介護費用の獲得など)といった専門家に相談することで、ケアに伴う費用負担や今後の生活設計について不安を軽減することができます。
交通事故などで負った怪我に対して、医学的に承認された治療を続けても、これ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。
この判断は主に主治医がおこないます。
症状固定後に、後遺障害等級の認定を受ける手続きをおこないます。
遷延性意識障害は、後遺障害の中でも最も重い後遺障害等級に認定される可能性が高いです。
具体的には、労働能力の喪失率が100%とみなされることが多く、後遺障害等級において最も症状の重い1級と認定されるケースが少なくありません。
認定された等級が重いほど、被害者は大きな賠償金を請求できる可能性がありますが、その一方で認定手続きは複雑になることがあり、医師による正確な診断書や画像資料などをもとに、賠償金獲得に向けた戦略的な交渉が必要となります。
通常、1級1号に該当すると認定されることが多くなっています。
後遺障害1級の認定は他の等級と比較しても非常に厳格な基準が適用されるため、医療機関での診断結果や日常ケアの記録が重要となります。
被害者が適切な等級認定を受けられれば、終身的かつ継続的な介護費や看護費についても保障を受けやすくなるでしょう。
なお、後遺障害等級に基づく慰謝料の相場は3つあります。
結論として、被害者にとってもっとも有利な相場は「弁護士基準(裁判基準)」により算定された金額です。
これは、交通事故被害の裁判の中で確立された基準で、自賠責基準や任意保険会社基準と言った他の慰謝料の基準よりも2倍以上高い金額となっています。
この弁護士基準は弁護士が主張して初めて、加害者が加入する任意保険会社に対して有効となる基準です。
弁護士が代理人となることで、保険会社は裁判による解決を意識することになり、費用や手間を考えると弁護士との交渉に応じざるを得なくなります。
遷延性意識障害の弁護士基準による相場は、110万円~2800万円となります。
参照 遷延性意識障害で認定される可能性がある後遺障害等級認
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
後遺障害認定基準 |
|---|---|---|
| 要介護1級1号(別表第1) | 2800万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 要介護2級1号(別表第1) | 2370万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級3号(別表第2) | 1990万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級2号(別表第2) | 1400万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級4号(別表第2) | 1000万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 9級10号(別表第2) | 690万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの |
| 12級13号(別表第2) | 290万円 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号(別表第2) | 110万円 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険会社に直接請求を行う『被害者請求』という方法があります。
被害者請求とは、交通事故の被害者が直接自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者自身が必要書類を準備し、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に提出します
これに対して、加害者側の任意保険会社を通しておこなう「事前認定」があります。
被害者にとって、適切な等級認定を受けられる可能性が高まるのは「被害者請求」です。
参照 「被害者請求」と「事前認定」の手続き比較
| 手続き | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 被害者請求 | ①提出書類の内容を自分で精査できる 必要な資料を自ら揃え、等級認定に有利な証拠の添付、不足情報を補足できるため、適正な認定につながる可能性が高まる。 ②自賠責限度額を先取りできる 示談成立前に等級に応じた保険金を受け取れ、当座の治療費などに充てられる。 |
多くの資料を自ら集める必要があるなど、手間と費用がかかる。 |
| 事前認定 | 保険会社側で手続きをおこなうため、書類作成や資料収集の手間が少ない。 | ①書類の不備や検査の不足が起きやすい 必要最低限の書類のみが提出される傾向があるなど、被害者が提出資料を把握しにくいといった手続内容の不透明性がある。 ②自賠責保険の限度額の支払いが示談後になる 支払いまでに時間がかかる ③低い等級になる可能性がある 被害者に有利な証拠を添付してもらえない可能性があり、その結果低い等級認定になる可能性がある。 |
被害者請求は、被害者にとって有利となるポイントが多いものの、後遺障害診断書や画像資料の収集、書類作成など多くの作業が必要となります。
そのため、後遺障害等級の専門家である弁護士に依頼し、適切に手続きを進めることが望ましいでしょう。
遷延性意識障害の被害者本人が意思決定能力や判断能力を失っている場合、有効な法律行為をおこなうことができないため、加害者やその加入する任意保険会社に対して損害賠償請求をおこなうこともできません。
そのため、被害者本人に代わって損害賠償請求をおこなう「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
この成年後見人を立てることで、被害者の代わりに交渉や訴訟などを行うことが可能になります。
選任手続きは家庭裁判所で行われますが、書類の準備や審査には一定の期間がかかるため、早めの対策が重要です。
なお、この選任にかかった費用は損害賠償請求の項目に含めることができます。
遷延性意識障害となってしまった場合、被害者や家族が請求できる賠償金にはさまざまな種類があります。
重度の後遺症が残ると、長期にわたりリハビリや介護が必要になります。
こうした費用負担は家族の生活面に大きな影響を及ぼしますが、適正な賠償金を請求することで金銭的な負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、代表的な賠償金の種類と主なポイントを整理し、漏れのないように請求手続きを進めるための知識をお伝えします。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
その相場は、弁護士基準で110万円(14級9号)~2800万円(1級1号)となっています。
遷延性意識障害に認定される場合は、最も重い等級1級となることが多く、慰謝料額も高額になります。
保険会社の提示金額と弁護士が算定する基準額には差が出ることが多いため、専門家による適切な評価を受けるとより高い慰謝料が期待できる場合があります。
逸失利益は、本来ならば将来にわたって得られたはずの収入が、後遺障害により失われることを金銭的に評価したものです。
遷延性意識障害の場合、労働能力の喪失が100%とみなされるため、余命や就労可能年数を考慮した非常に大きな金額が算定されることがあります。
計算の過程では、年齢や職業、平均賃金など多角的な視点で検討されるため、資料を正確に用意することが重要です。
なお、前述したとおり遷延性意識障害の方は平均余命よりも短い期間で亡くなることがあるため、相手方の保険会社から平均余命よりも短い期間で算定された逸失利益を主張されることがあります。
しかし、保険会社の主張が不当である場合には、担当医師の医学的見地からの所見などをもとに、しっかりと丁寧に反論をおこなうことが適切な賠償を受けるうえでとても大切です。
この保険会社が平均余命期間よりも短く算定し主張するものとして、介護費用など将来に渡り必要となる項目があるので注意が必要です。
遷延性意識障害の治療は長期におよぶことがあり、入院費用や雑費(おむつやカテーテルなどの実費)、通院時の交通費、付添看護が必要な場合の費用などが発生します。
また、精神的な苦痛に対して支払われる入通院慰謝料も請求できる可能性があります。
これらは実際に支払った領収書や通院記録などが必要となるため、日頃から領収書の保管などをしておくことが大切です。
休業損害は被害者が事故によって仕事を休まざるを得なくなった場合に認められる損害費用であり、休業期間中の収入減少を補填する目的で支払われます。
遷延性意識障害を負うほどの大事故では、長期休業どころか就労が困難な状態になることがほとんどです。
収入証明や医師の診断書などが必要となるため、事前に十分準備しましょう。
遷延性意識障害の被害者は、継続的な介護や通院はもちろん、自宅での介護を行うためのバリアフリー化や設備導入が必要になる場合があります。
例えば、車いす対応のリフォームや介護用ベッドの設置などにかかる費用も、損害賠償の対象となることが一般的です。
将来的な費用をしっかりと見積もり、加害者側に請求することで、被害者や家族の負担を少しでも軽減できる可能性があります。
重大な後遺症が残る事案では、適切な補償を得るために弁護士に依頼することも選択肢のひとつです。
遷延性意識障害のように最重度の後遺障害が認められるケースでは、保険会社との交渉や裁判が長期化する傾向があります。
医療記録や後遺障害診断書の内容が複雑であるため、素人がすべてを把握して正しい損害賠償金額を算出するのは困難です。
弁護士に相談することで、法的知識と交渉力を活用し、より確実に公正な金額を獲得することが期待できます。
また、最近では加入する任意保険に「弁護士費用特約」が附帯されていることも多く、この特約を利用することで弁護士への相談や依頼費用が補填されます。
一般的に保険会社が提示する金額と、弁護士が独自に算定する『弁護士基準』では金額に大きな差が生じることがあります。
加害者が加入する保険会社にとって、被害者に対する賠償金の支払いを低く抑えることは利益となります。
そのため、提示された賠償額が著しく被害者にとって不利なケースが多く見られます。
とくに後遺障害1級が認定されるほどの重度な障害の場合、その差は顕著です。
弁護士基準による請求を行えば、加害者側との交渉が難航しても適切な解決が可能となり、結果的に増額を勝ち取る確率が高まります。
保険会社との交渉や書類作成など、交通事故の被害者が直接対応するには大きな負担がかかります。
重度の後遺症がある場合、家族が介護に注力しなければならず、加害者側の保険会社との交渉に割ける時間も精神的余裕も限られてしまうことが多いです。
弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社の担当者による心ない対応や、しつこい電話対応も代理人として交渉を行ってくれるため、被害者さまの家族が抱える精神的な負担を大きく軽減することができます。
後遺障害等級認定に必要な書類や手続き、さらには成年後見人の選任申立など、専門知識が求められる事務作業が多数発生します。
このような手続きを誤ると、認定が遅れたり賠償金交渉に不利になったりするリスクがあります。
弁護士に手続きを代行してもらうことで、申請ミスを防ぎながら的確な準備を進めることができ、家族は看護と生活に集中しやすくなるでしょう。
古山綜合法律事務所には、損害保険会社の元代理人弁護士が在籍しています。
今は、被害者専門で交通事故の問題を取り扱い、後遺障害等級認定手続きから、加害者側との示談交渉や裁判手続きまでフルサポートさせて頂いています。
遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度後遺障害による損害賠償請求にも対応しています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、交通事故被害の初回無料法律相談も実施中です。
無料相談の中で、ご状況やご希望を丁寧にお伺いし、① 後遺障害等級の等級診断、② 賠償金の試算、③ 解決策の提案と今後の流れについて、説明やアドバイスをさせて頂いています。
重度後遺障害は全国対応も可能です。
オンライン相談もおこなっておりますので、ご予約のうえご相談ください。
古山綜合法律事務所が交通事故被害に強い理由
1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応
保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心。
2.専門誌掲載の実績
代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当した裁判が掲載されました。
その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。
3.交通事故被害専門のサポート
被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。
交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。
 072-800-1522
072-800-1522
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。