 072-800-1522
072-800-1522着手金
コラム詳細
目次
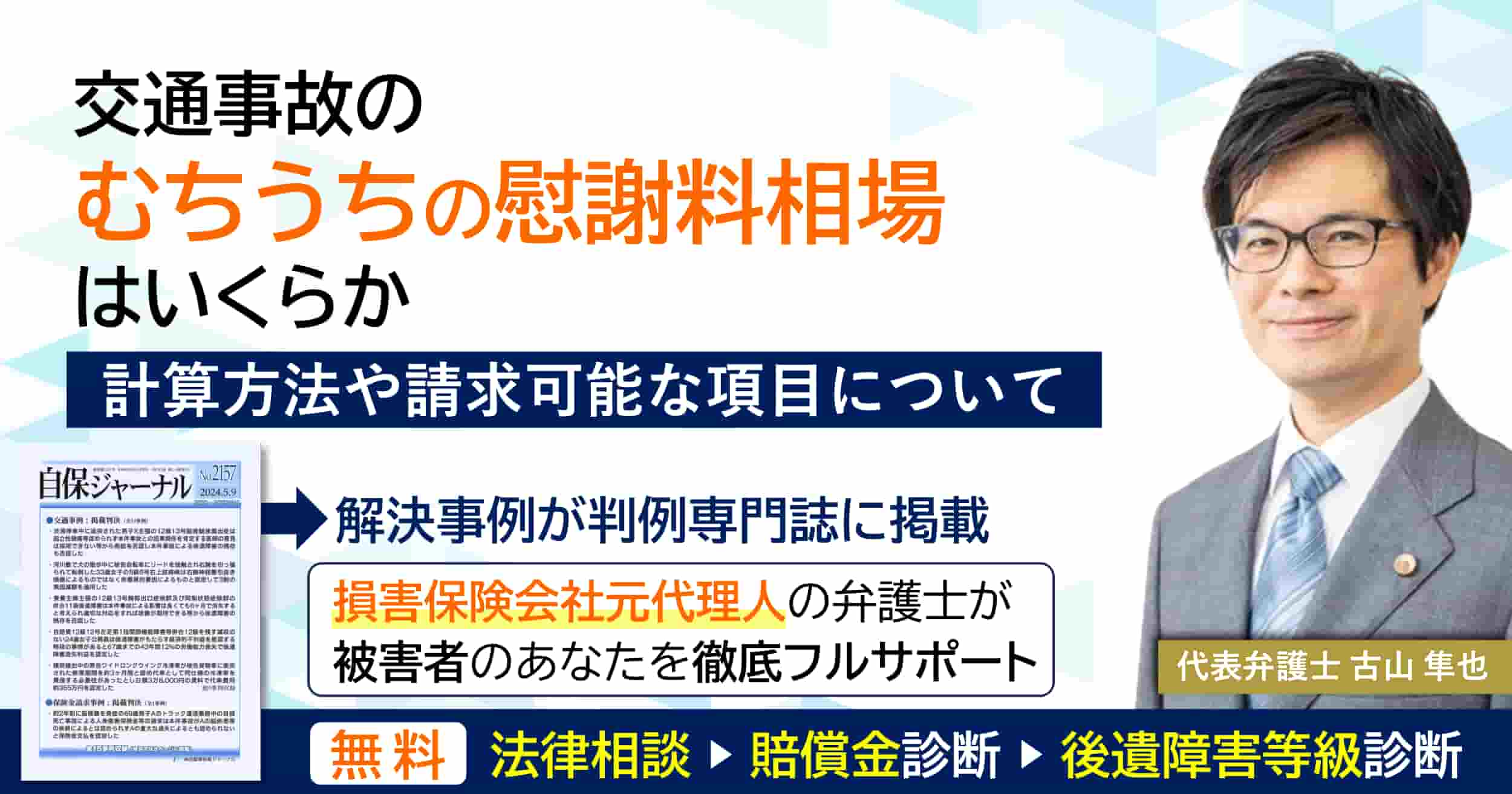
交通事故被害による「むちうち」の後遺障害等級と慰謝料相場
交通事故によるむちうち被害に遭った際、慰謝料の相場や請求方法が分からないという方も多いでしょう。
むちうちは追突事故などで頻繁に起こるケガで、そのため慰謝料請求の際には正しい知識が重要です。
慰謝料額は、自賠責基準、保険会社基準、そして弁護士基準という3つの基準によって大きく異なり、自身のケースに応じた適切な対応が必要です。
本記事では、むちうちの慰謝料相場の解説に加え、計算方法や請求可能な各項目について詳しくお話しします。被害者の方々において適切な補償を受け取るための基礎知識としてぜひ参考にしてください。
むち打ちは交通事故の中でも特に多い怪我です。レントゲンなどの画像検査などで原因や症状を確認できないケースも多く、保険会社から低い賠償額を提示されることも珍しくありません。
そうした事案でも、当コラムで解説しているような後遺障害等級認定申請(異議申立て)などをおこない、加害者に対して賠償請求できる各項目について、被害者にとって一番有利な弁護士基準で算定し直すことで、全体的に賠償金を増額させることも可能となります。
ぜひ、むち打ちの症状でお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
ご状況、ご希望を踏まえて、具体的な解決策をご提案いたします。
保険会社側元代理人 弁護士 古山 隼也
むちうちの被害に遭った際、慰謝料の適正な相場を知ることは重要です。
加害者や保険会社との交渉で自分の権利を守るためにも、正確な知識を持ちましょう。
むちうちの慰謝料の相場を算定には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3つの基準があります。
結論としては、弁護士基準が被害者にとって最も有利な基準となっています。
交通事故における「むちうち」の慰謝料には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3種類の基準が存在します。
これらの基準は、それぞれ慰謝料を算出する際の額に大きな違いをもたらし、被害者にとっての補償額に直接影響を与えます。
✔ 自賠責基準
国の強制加入の制度であり、最低限の補償(基準)。
自動車損害賠償保障法施行令で定められているため、支払額には上限がある
✔ 保険会社基準(任意保険基準)
任意保険会社独自の基準であり、自賠責基準の額に少し上乗せされた金額であることが多い。
✔ 弁護士基準(裁判基準)
交通事故被害の裁判の中で確立された基準で、自賠責基準の2倍以上となっている。
ほぼ自賠責基準と変わらない保険会社基準と比べて「被害者にとって最も有利」な基準。
むちうちが後遺障害として認定を受けることができると、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の等級は「自動車損害賠償保障法施行令別表」により、症状が一番重い1級から14級に区分されています。
むちうちの後遺障害は、申請書類を受け取った損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」による等級認定手続きを経て、「12級13号」「14級9号」「非該当」のいずれかが判断されます。
該当する等級で、自賠責基準と弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料を比較すると次の通りです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準・裁判基準) |
|---|---|---|
| 12級13号 | 32万円 | 110万円程度 |
| 14級9号 |
94万円 ※ 2020年3月31日までに発生した事故の場合 93万円 |
290万円程度 |
自賠責基準は、最低限の補償を目的として設定されています。そのため支払われる慰謝料は基本的に低めに抑えられており、事故の被害者全員が等しく一定の保障を受けられるようにされています。
任意保険会社は、支払いを低く抑えることが会社の利益になります。
そのため、任意保険会社を通して自賠責と合わせて提示される金額は、上記の自賠責基準に多少上乗せされた金額になることが予想されます。
一方で、弁護士基準は裁判での判例や裁判所が認めた額を基にしているため、最も高額な慰謝料を得られる可能性があります。
この基準は、公平性や客観性に基づいて計算されるため、保険会社が提示する額よりも高額になるケースが多いです。
ただ、この弁護士基準による交渉は、弁護士が主張して初めて効力を持ちます。
弁護士が介入することで、保険会社は任意交渉の段階でも「裁判」を意識した上で交渉せざるを得ず、弁護士の主張する内容や証拠をもって弁護士基準での支払いに応じることとなります。
なお、弁護士基準は裁判基準とも言われることがありますが、必ず裁判をする必要はありません。
弁護士に依頼する=裁判、というイメージがあるかもしませんが、解決方法としては交渉による弁護士基準での示談解決の方が多いと言えます。
そのため、適切な補償や有利な条件を引き出すためにも、弁護士の法律相談を受け、増額の可能性についてアドバイスを受けておくことをおすすめします。
交通事故によるむちうちの慰謝料計算は、いくつもの項目にまたがることもあり、一般の方にとっては複雑なものです。
請求可能な項目や計算方法を把握し適切に進めましょう。
なお、当事務所では初回無料相談にて、あなたのご状況に応じた慰謝料増額の可能性について診断をおこなっています。ぜひお気軽にご相談ください。
「むちうち」で請求可能な項目
✔ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
✔ 後遺障害慰謝料
✔ 後遺障害逸失利益
✔ 休業損害
✔ その他項目
・治療費
・通院交通費
・文書、雑費
交通事故でむちうちを負った場合、適切な慰謝料を請求するには、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、通院交通費など、請求可能な項目を理解することが重要です。
交通事故でむちうちの被害を受けた場合、入通院慰謝料は治療や通院に伴う精神的・肉体的苦痛への補償となります。
後述する後遺障害慰謝料と異なり、後遺障害として認定されていなくても交通事故被害で傷害を負ったことに対する慰謝料であり、通院日数や入通院期間の長短により金額が決まります。
この入通院慰謝料についても、自賠責基準 、弁護士基準があります。
入通院慰謝料について比較してみましょう。
事例 むちうち被害者の通院状況
① 通院期間 3か月(90日)
② 実通院日数 40日
③ 入院なし
自賠責基準での計算式は次の通りです。
計算式:日額4300円×対象日数
※2020年3月31日以前の事故は日額4200円
※但し、対象日数の計算について、次のうち少ない方とする
(A)通院期間
(B)実通院日数の2倍
※ 自賠責保険の慰謝料早見表
むちうち(軽症)の場合で、通院期間3ヶ月(90日)の場合
| 実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
|---|---|---|
| 10日 | 8万6000円 | 53万円 |
| 20日 | 17万2000円 | 53万円 |
| 30日 | 25万8000円 | 53万円 |
| 45日 | 38万7000円 | 53万円 |
| 50日 | 38万7000円 | 53万円 |
| 70日 | 38万7000円 | 53万円 |
通院期間は90日、実通院日数の2倍は80日です。
日数として少ない80日を対象日数として、計算式に当てはめて算定します。
自賠責基準の入通院慰謝料
80日×4300円=34万4000円
他方、弁護士基準は東京地方裁判所の実務に基づき賠償額の基準を掲載している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(通称 赤い本)の算定表「別表Ⅱ入通院慰謝料基準」をもとに計算します。
下記は、むちうちなど軽傷の場合に用いられる慰謝料算定表です。

今回の事例では「むちうちで入院なし、通院期間3か月」の場合、弁護士基準による入通院慰謝料は53万円となります。
自賠責基準による入通院慰謝料に比べて、18万6000円高くなります。
弁護士基準による入通院慰謝料は「適切な通院期間の確保」が重要なポイントであることが理解いただけたと思います。
保険会社は 治療が一定以上長期間におよぶ時には、治療費の打ち切りの打診をおこなってくることがあります。
しかし、安易に治療費の打ち切りに応じることはありません。
治療継続の要否は、医師が判断するものです。
担当医が治療を継続する必要があると診断された場合、根拠となる医療記録や医師の診断書を利用して、治療の正当性を保険会社に伝えると良いでしょう。
それでも治療費が打ち切られた場合には、費用を立て替え自己負担で治療を継続することを検討しましょう。
治療費打ち切りにより、本来必要な治療を断念してしまうことで、入通院期間が短くなり入通院慰謝料が低額になり、後遺症が残った場合にする後遺障害等級認定手続きで、適切な等級認定を受けられなくなる可能性があります。
なお、保険会社が治療費打ち切りをした場合、保険会社が病院へ治療費を直接支払う「一括対応」は終了します。
ただ、加害者が加入する任意保険会社ではなく、自賠責保険に立て替えた治療費を請求することができます。
また、状況が複雑である場合や保険会社との交渉が難航する場合には、弁護士に相談することを検討するのも一つの対応です。
弁護士は専門的な知識を持ち、法的知識に基づいたアドバイスや代理交渉をおこなうことも可能です。
保険会社による治療費打ち切りに直面した場合、適切かつ冷静な対応が必要です。
事故被害者としての権利を守りながら、継続的な治療を受けるための対応策を検討しましょう。
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残る被害者の身体的・精神的 苦痛を補償するための慰謝料です。
後遺障害等級が認定されるとその等級に応じた慰謝料が算定され、等級が高いほど慰謝料も増加します。
等級は1級から14級まであり、適切な請求手続きによる等級認定が慰謝料増額のカギとなります。
後遺障害慰謝料には、認定される等級によってその金額に大きな違いが生じます。
前述したとおり、12級13号は自賠責基準「94万円」、弁護士基準「290万円程度」。14級9号では自賠責基準「32万円」、弁護士基準「110万円程度」と、その差は明確です。
12級13号と14級9号の認定の差は、次の通りです。
| 12級13号 | 14級9号 | |
|---|---|---|
| 認定基準の違い | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 局部に神経症状を残すもの |
|
医学的証明の程度 |
神経症状の存在を医学的に「証明」できる必要がある |
神経症状の存在が医学的に「説明」できれば認定される可能性がある |
|
画像所見と神経学的検査 |
・画像検査(MRIやレントゲン)で異常所見が必要 ・神経学的検査で明確な異常が必要 |
・画像検査で異常所見がなくても認定される可能性あり ・神経学的検査で異常が示唆されれば可 |
つまり簡単に言えば、画像検査などで明らかに異常が認められる場合は12級13号、検査結果などにより他覚所見は見られず客観的証拠はないものの、症状の一貫性があり医学的に説明がつく場合には14級9号が認定される可能性があります。
14級9号について、継続的な通院歴や治療経過の一貫性が重視されるため、治療継続が必要であるにも関わらず保険会社の治療費打ち切りに応じてしまうことで、14級9号さえ認定されず、後遺障害の認定が前提となる後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなるリスクが高くなります。
そのため、症状の一貫性・継続性については、医師作成の後遺障害診断書の記載から判断されるため、普段から医師に対して生活や仕事にどのような影響が出ているのかを通して自覚症状を伝えて、診断書に記載をしてもらえるようにお願いします。
このように、入通院段階から、症状に合った慰謝料を獲得するための行動が大切になります。
むちうちで請求できる項目は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料のほか、治療費、通院交通費、休業損害、後遺障害逸失利益、文書料や雑費など多岐に渡ります。
休業損害は、交通事故による休業期間中において働けなくなったことで発生した損失を補填するものです。
失業者、主婦(主夫)・パート、自営業者(無申告、実収入が申告額より多い場合も含みます )、学生の場合でも、休養損害を獲得できる場合があります。
休業損害もまた、自賠責基準、弁護士基準があります。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 原則 6100円 ※6100円を超える証明資料があれば、上限19000円を限度に支払い |
事故直前3か月の給与総額÷稼働日数×休業日数 ※ 自賠責と異なり、上限なく支給 |
具体的には、給与所得者の場合、事故前の月収を基準として日割り計算が行われます。
また、事業所得者においては、過去の所得申告額を基準として、収入減少分の補償がおこなわれます。
さらに、主婦や無職の場合でも、家事労働の価値や将来的な就労可能性が考慮され、休業損害が認められるケースがあります。
このように、休業損害は、さまざまな生活スタイルや職業形態に対応して幅広く適用されるのが特徴です。
休業損害を請求する際には、事故との因果関係や収入減少の証明が重要です。
給与明細書や確定申告書などの資料を適切に用意することで、スムーズな請求手続きが可能となります。
休業損害の適正な補償を受けるためには、早い段階で専門家や弁護士に相談することも有効と言えるでしょう。
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって生涯にわたって得られるはずだった利益(収入)が、後遺障害の影響で失われる場合に保証されるものを指します。
これは被害者の将来的な経済的損失を金銭で補填するためのものです。
前述の「休業損害」は入通院期間の補償であり、治療を継続してもこれ以上症状が改善しないと判断された症状固定以降、後遺障害による将来的な減収に対して「逸失利益」として補償を求めることになります。
後遺障害が認定されると、被害者の労働能力が喪失して、生涯の収入に大きな差が生じたと認められます。
後遺障害逸失利益の計算にあたっては、基礎収入、労働能力喪失率、就労可能期間を考慮し、ライプニッツ係数を使用して算定を行います。
むちうちによる後遺障害逸失利益は次の計算式で算定します。
① 基礎収入 × ② 労働能力喪失率 × ③ 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
①基礎収入は、例えば会社員であれば、基本的に前年の基礎年収になります。主婦(主夫)の場合には、賃金センサス(毎年政府が公表する平均収入の資料)を用いて計算します。
②労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて目安が決まっています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
ただ、後遺障害の内容や職種によって別の取り扱いになるケースがあります。
そのため逸失利益の計算は複雑であり、確実に算定をおこなうために交通事故被害に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
特に、後遺障害に関わる逸失利益は将来の補償であり、その生活に大きな支障をきたす可能性があるため、この点への配慮は欠かせません。
当事務所でも、保険会社提示の賠償額についてのチェックをおこなっています。
ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。
交通事故によるむちうちの場合、休業損害、逸失利益などのほか治療費に関する項目についても、加害者側に請求することが可能です。
前述しましたが、治療費を請求することが可能です。
具体的には、診察料、薬代、リハビリテーション費用といった項目が治療費として請求可能です。
整形外科での診療や理学療法士による治療はもちろんのこと、むちうちの治療に必要な各種の診療行為が対象となります。
これにはレントゲンやMRIといった画像診断費用も含まれます。
通院交通費として請求できる金額には、例えば、電車やバスなどの公共交通機関を使用した場合、その料金を領収書や移動記録とともに請求することが可能です。
また、自家用車を使用して通院した場合も、走行距離に基づいてガソリン代や駐車料金が認められる場合があります。
この際、通院に必要であったことを立証できる記録を保管しておくことが求められます。
通院の日時や交通手段、支払った金額をしっかりと記録し、その記録に基づいて主張することがポイントとなります。
文書料として、診断書や証明書といった文書を作成するための費用を請求できます。
請求の具体例としては、医師が発行する診断書や診療記録のコピー費用、敬意事件記録の取得費用、鑑定書の作成料など損害賠償請求や保険金請求の際に必要となる文書代が含まれます。
また、入院中の日用品費(歯ブラシ、タオル等)、通院時の駐車場代などの入院雑費も請求可能です。
入院雑費については、基本的に日額1500円で計算して請求します(自賠責基準では日額1100円です)。
むちうちの慰謝料を増額するためには、いくつかポイントがあります。
交通事故において、むちうちなどの怪我を負った場合、人身事故として警察に届出をすることは非常に重要です。
むちうちは時間経過とともに症状が表れることもあります。
事故直後に症状がなくても、必ず医療機関を受診しましょう。
加害者から物損で処理して欲しいと言われることがありますが、物損事故(物件事故)として届け出をしてしまうと交通事故被害者にとって次のデメリットがあります。
・加害者に刑事処分などの責任追及が難しくなる
・実況見分調書が作成されない
事故状況の正確な記録が残らず、後の交渉で不利になる可能性がある。
実況見分調書は事故の発生状況を記録したもので、事故と受傷との因果関係や過失割合などにおいて重要な資料となります。
加害者から「治療費を支払うので、物損事故で届出して欲しい」とお願いされるケースがあります。
しかし、ケガがあるのに物損事故で届出をすることに、被害者にとってメリットはありません。
怪我をしているのにわざわざ物損事故として届け出をしたことから、保険会社から「怪我の程度がたいしたことなかったから物損事故として届け出たのでしょう」などと言われるおそれがあり、後遺障害の等級認定にとっても足を引っ張る可能性がありますので、怪我をしているのであれば人身事故として届け出るほうがよいでしょう。
前述した通り、入通院慰謝料は入院・通院日数に比例して増えていきます。
症状に応じて治療期間を確保することが大切です。
また、12級として認定されるためには、MRIやCTスキャンなどの画像診断や神経学的検査により他覚所見があることが必要であり、後遺障害等級認定を見すえて、適切な検査を受けておくことが必要です。
これにより、適切な治療方法を医師が判断しやすくなるだけでなく、後に慰謝料請求を行う際にも必要な根拠となります。
こうしたことから自分の判断で治療を中断することや、適切な検査を受けずにいることは、保険会社との交渉や補償請求の段階で不利に働く可能性があります。
むちうちが後遺症として残った場合、後遺障害等級の申請をおこないます。
申請方法は、加害者が加入する任意保険会社を通しておこなう「事前認定」、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に申請をおこなう「被害者請求」があります。
申請の手間がかかるものの、基本的に「被害者請求」による申請がよりメリットが大きいです。
事前認定では、後遺障害等級認定に必要な書類がきちんと提出されたか、被害者側で正確に把握できません。
これに対して、被害者請求は提出書類を自ら判断、不備がないかを事前に把握することができ、後遺障害等級が認定されるよう等級認定の審査の対策ができます。
また、被害者請求では後遺障害認定終了後、加害者側の自賠責保険会社から一部の賠償金を先行して受け取ることができます。
事前認定では、全額の支払いが示談成立後になります。
このように、適切な等級認定手続き、賠償金の一部先行して支払いが受けられるという点で「被害者請求」をおすすめします。
交通事故でむちうちに遭った際、弁護士に依頼すれば、保険会社のプロ担当者と慰謝料の増額交渉を代行してもらうことができ、有利な解決を図ることが期待できます。
また、後遺障害等級認定手続きのサポートや証拠収集のアドバイスを受けることができます。
弁護士が「弁護士基準」を用いて主張することで、保険会社基準よりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。
保険会社の担当者は交通事故に関する交渉の専門家です。
そのため、一般人である被害者自身が保険会相手に交渉にあたると、知識や経験の不足から提示される慰謝料が適正な金額よりも低くなるリスクがあります。
保険会社は被害者の苦痛や損害を補償する義務がありますが、その一方で保険会社の利益を守るために支払い金額を抑えようとするのも事実です。
弁護士を代理人として立てることで、保険会社のプロ担当者に対抗することが可能です。
弁護士は法律の専門知識と交渉の経験が豊富であり、慰謝料計算や賠償金請求の適正性を主張することが可能です。
後述する「弁護士費用特約」に加入し利用できる場合は、弁護士費用の心配をすることなく弁護士に依頼できます。
医師は治療のプロですが、後遺障害等級認定申請のプロではありません。
等級認定申請に必要な後遺障害診断書にどのような記載が必要か、どういった検査が必要かなどについての判断は、弁護士が詳しいと言えます。
中でも後遺障害等級認定手続の代行に弁護士を依頼することで、手続のスムーズさと精度が大幅に向上します。後遺障害等級認定には、医療記録や事故発生状況報告書など専門的な書類が必要であり、被害者自身で進めようとすると多くの負担が発生します。
認定手続が重要なのは、認定される後遺障害の等級によって慰謝料や補償額が大きく異なるためです。
たとえば、後遺障害が適切に認定されれば、被害者が受け取れる慰謝料や損害賠償金の金額は増加します。
弁護士は豊富な経験と法律の知識を活用し、医師と連携して必要な診断書や証拠書類を整え、正確に申請を進めることができます。
当事務所には、保険会社の元代理人弁護士が在籍しています。
後遺障害等級認定申請に関して、フルサポートをおこなっています。
ぜひ、等級認定でお悩みの方はご相談、ご依頼ください。
弁護士費用特約に加入している場合、弁護士への依頼に必要なコストを気にせず進めることができます。
弁護士費用特約は、発生した弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれる保険制度であり、依頼者の自己負担は軽くなり、弁護士への相談や依頼のハードルが非常に低くなります。
自動車保険や火災保険の特約として付帯されていることがあり、加害者自身だけでなく、ご家族が付帯している場合でも利用できる場合があります。
一度、ご自身やご家族で加入しているか、約款上利用可能かどうかを確認されると良いでしょう。
基本的に、相談料は10万円、着手金・報酬金といった弁護士費用は300万円までを上限として補償されることが多いです。
特約に加入している場合、最大限にその制度を活用し、交通事故問題を弁護士に適切にサポートしてもらうことで、有利な解決を目指すことができます。
交通事故後の慰謝料請求では、保険会社が様々な理由をつけて減額を主張する場合があります。
減額される背景には、保険会社が経済的利益を守るための手段として、通院日数や症状の軽さ、既往症の影響など、考えられる減額要素を検討していることが挙げられます。
このようなケースを事前に理解し適切な対応を取ることが、減額を防ぐための重要なポイントとなります。
通院日数が短い場合、保険会社は慰謝料の減額を主張する可能性があります。
これは、入通院慰謝料の算定において通院の頻度や期間が重要な要素となるためです。
通院が少ない場合、保険会社から「治療の必要性が低かった」と判断されることがあり、それによって適正と思われる金額から減額される場合があります。
合わせて、前述のとおり自賠責基準での日額で計算し示談案を提示されることが多いです。
ただ、通院日数=通院回数が多いほど、慰謝料が増えるわけではなく、週2回から3回程度の通院をしていれば、通院期間として計算でき、弁護士基準での慰謝料の支払いを求めることは可能です。
通院頻度については、担当医師と相談し通院されると良いでしょう。
そのため、適切な証明資料や診断書を揃えて、反論することが重要なポイントとなります。
具体的には、治療の必要性や通院の目的を詳細に書き記した医師の診断書や検査結果が有効です。
また、痛みや不調の度合いを診療結果として残し客観的な証拠とすることも必要で、通院先との連携を密にすることも求められます。
適正な慰謝料を請求するためには、通院の正当性を立証し、治療が必要不可欠であったことを保険会社に明確に伝えることが必要です。
被害者に既往症や持病がある場合には、その慰謝料が減額される可能性があります。
交通事故被害以前から、被害者に病気(既往症)があり、事故の損害が拡大した場合には、既往症が影響した部分については損害額から差し引きます。これを「素因減額(そいんげんがく)」と言います。
保険会社は、被害者の症状が事故以前から存在していた問題による影響と主張し、慰謝料の減額を図ることがあります。
例えば、被害者がむちうち症の診断を受けた際に、もともと頚椎に問題を抱えていた場合、保険会社はその持病が事故の影響を増幅したと判断し、慰謝料の減額を求めてくる場合があります。
このような主張がなされることで、本来請求すべき慰謝料額が減少するリスクが存在します。
この素因減額は、加害者側が立証する必要があります。
裁判になった場合、交通事故の状況や事故車両の損傷状況、既往症の内容や程度などを踏まえて判断されることになります。
こうした場合には、法律の専門家である弁護士に相談することが有益です。
弁護士は、既往症や持病に起因して支払額が減額への対策や、保険会社との交渉を有利に進めたりする上で専門的なアドバイスやサポートをおこなうことができます。
被害者側に過失がある場合、慰謝料が減額される可能性があります。
被害者側にも一定の責任が認められる場合には、加害者が負担する賠償額が減額し、損害を公平に分担することとなります。
たとえば、信号無視や不注意な道路横断など、被害者の行動が事故の原因の一部となった場合、過失割合に応じて加害者側が支払うべき慰謝料が減少することがあります。
ただ、保険会社が主張する過失割合も、交渉により修正が図られる可能性はあります。
そのため、被害者としては適切な証拠を収集し、主張することで過失割合を見直し、不当に慰謝料が減額されることを防ぐ必要があります。
専門家である弁護士に相談することで、過失相殺の説明や証拠収集といったサポートを受けることが可能です。
前述したとおり専業主婦であっても、交通事故により休業損害などの慰謝料請求が可能です。
一般的に専業主婦は収入がないため、損害賠償が請求できないと誤解されることがありますが、家事労働にも経済的価値が認められています。
そのため、裁判所では専業主婦の家事労働を職業労働と同等に評価し、損害として考慮される場合があります。
接骨院、整骨院は名称が異なるだけで、施術をおこなうことに違いはありません。
ただ、接骨院や整骨院は医療行為をする医療機関でなく、施術も医師でなく柔道整復師によるものであることなどから、接骨院または整骨院のみに通院した場合、その費用が認められなくなる可能性が高まります。
まずは、医師による診察があり、画像検査などを行える整形外科などへの通院をおすすめします。
適切な治療として整骨院の通院が必要であると医師の判断・指示がある場合に、整骨院に通院するようにしましょう。
医師から接骨院や整骨院への通院を許可されていない場合、慰謝料が減額される可能性が高まります。これは、保険会社が医師の診断や指示に基づかない治療を「必要のないもの」として判断し、その治療の正当性が認められないケースがあるからです。
整骨院の施術費用の支払いや、通院回数として含めて算定するために次の点について押さえておく必要があります。
① 病院に通院後、整骨院の施術が必要であると診断・判断を受けること
② 整骨院の通院と並行して、病院にも通院すること
③ 整骨院通院について、保険会社に伝えること
むちうちの治療のため、医学的に必要であると判断されたことをベースにして、保険会社に通知することで慰謝料に通院内容は反映されることとなります。
いずれにせよ、整骨院の施術に対する補償などは、保険会社とトラブルになるケースもあるため注意が必要です。
この記事では、交通事故によるむちうちの慰謝料の相場や算出方法、どういった項目が請求可能かについて詳しく解説しました。
入通院慰謝料や治療費の実費、後遺障害等級の認定を受けた際の後遺障害慰謝料と逸失利益などについて、保険会社提示の示談案について検討し、弁護士基準で再計算してみることが慰謝料増額のために必要なステップとなります。
当事務所では、交通事故被害者の方にとって難しい示談案の適性診断、後遺障害等級の見立て(等級認定の獲得の可能性)などについて、初回相談で実施しています。
ご事情やご状況に応じて、具体的な解決アドバイスをおこなっています。
ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所には、保険会社側の元代理人弁護士が在籍しており、保険会社の仕組みを熟知しており、賠償金増額について強みを持っております。
また、むちうちの交通事故被害について、慰謝料増額、等級認定獲得などの実績があります。
全国対応可能ですので、まずは電話やWEBフォーム、LINEからお気軽にお問い合わせください。
古山綜合法律事務所が交通事故被害に強い理由
1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応
保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心。
2.専門誌掲載の実績
代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当した裁判が掲載されました。
その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。
3.交通事故被害専門のサポート
被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。
交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。
 072-800-1522
072-800-1522
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。