 072-800-1522
072-800-1522着手金
コラム詳細
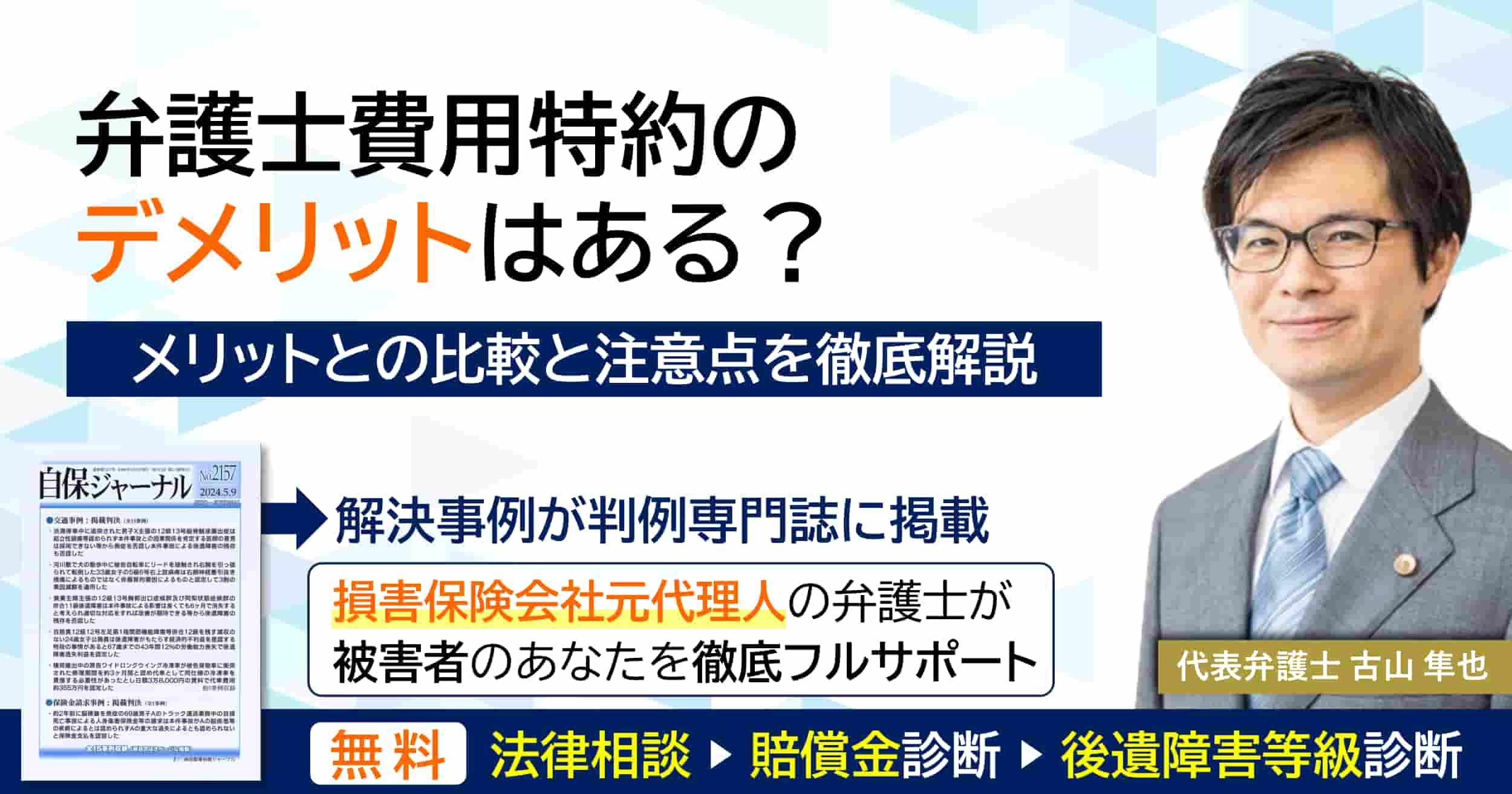
自動車保険などに付帯できる弁護士特約は、交通事故の示談交渉を費用負担少なく弁護士にまかせることができ、結果として適切な賠償金を獲得できるなど、多くのメリットがあります。
一方で、加入前・利用前に知っておきたいデメリットや注意点も存在します。
本記事では、弁護士特約の概要やメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、実際に特約が使えないケースや、弁護士特約利用が推奨される状況を具体的に挙げていきます。
弁護士特約を賢く使いこなすために、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士特約は、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯できるオプションで、交通事故などの損害賠償請求にかかる弁護士費用をカバーしてくれる仕組みです。
なお、保険に付帯する弁護士費用特約は、保険商品や保険会社によって適用範囲や補償範囲や条件が異なります。
自動車事故のみを補償対象とするタイプと、日常生活全般のトラブルを補償対象とするタイプがあります。
加入や利用前に、契約内容を十分確認しておきましょう。
弁護士特約は、交通事故の当事者が示談交渉や賠償請求の手続きを進める際に、弁護士へ支払う費用を保険会社が補償する制度です。
交通事故に不慣れな方でも、専門家である弁護士のサポートを得ることで煩雑な手続きをスムーズに進められる点が大きな強みといえます。
争点が多い事案や相手方が高圧的な態度をとる場合でも、弁護士が代理交渉をおこない、被害者の方にとって有利な条件をもって交渉を進めるため、賠償金増額の可能性が高まります。
弁護士費用特約が利用できる範囲は、事故に遭われたご本人(被保険者)だけでなく、その配偶者や同居のご家族なども補償の対象となるケースがあります。
対象となる費用の範囲も広く、示談交渉や法律相談にかかる費用はもちろん、裁判に進んだ場合の諸経費や弁護士への報酬なども補償されるのが一般的です。
ただし、具体的な対象範囲や、ここでいうご家族の定義はご加入の保険商品ごとに異なりますので、お手元の保険証券や約款をご確認いただくことが重要です。
参照 弁護士特約の一般的な補償対象例
弁護士費用特約では、着手金や成功報酬、訴訟費用などが補償対象となるのが一般的です。
多くの保険会社では300万円程度の上限が設定されているケースが多く、それを超える部分は自己負担となる点に注意が必要です。
実際の裁判費用だけでなく、法律相談や書類作成にかかる経費も含まれる場合があるため、事前にどこまでカバーされるのかを確認しておくと安心です。
参照 弁護士費用特約の一般的な補償金額
✅ 法律相談費用 10万円
一般的な上限金額は、1事故1名あたり10万円
✅ 弁護士費用 300万円
一般的な上限金額は、1事故1名あたり300万円
例 着手金(事件の依頼時にかかる費用)、成功報酬金(成功の程度により発生する報酬金)、日当(遠方の裁判所等に出廷・出張する際の費用)、実費(訴訟提起時の収入印紙代、郵便切手代、旅費交通費、通信費用など)
弁護士特約は自動車保険での利用が広く知られていますが、火災保険や住宅総合保険、傷害保険などでオプションとして用意されている場合もあります。
これらの保険では、日常生活でのトラブルや不動産に関する法的紛争に備える目的で追加できることが多いです。
自動車事故以外のリスクにも対応したい方は、複数の保険会社やプランを比較検討し、総合的な保険プランを構築するのがおすすめです。
参照 自動車保険以外に弁護士費用特約が付帯される可能性のある主な保険
・火災保険
日常生活における賠償トラブル(例:水漏れで階下の家財を汚損したなど)や、不動産に関するトラブルなどで利用できる場合があります。
・傷害保険
事故によるケガに関連するトラブルなどで利用できることがあります。
・医療保険
病気やケガに関するトラブルで弁護士に相談する必要が生じた場合などに補償されることがあります。
・個人賠償責任保険
日常生活での様々な賠償事故(例:自転車事故で他人にケガをさせた、飼い犬が他人に噛み付いたなど)に関するトラブルで弁護士費用が補償されることがあります。この特約は火災保険や傷害保険などにセットされていることも多いです。
・自転車保険
自転車事故に関するトラブルに特化した弁護士費用を補償するものがあります。
・バイク保険
自動車保険と同様に、バイク事故に関する弁護士費用を補償します。
相手方が任意保険に未加入であったり、過失割合をめぐってトラブルが生じたりした場合でも、弁護士が間に入ることでより円滑に示談交渉を進められます。
さらに、賠償金や慰謝料の増額が見込めることもあり、事故後のサポートのメリットが大きいといえます。
一方で、弁護士費用がかかることがデメリットですが、弁護士特約の最大の魅力は、高額になりがちな弁護士費用を保険会社が補償してくれる点です。
弁護士が介入することでどのようなメリットがあるのか、具体的に解説します。
参照 弁護士特約加入、弁護士依頼のメリット
✅ 精神的負担の軽減
弁護士が加害者や保険会社との交渉窓口となります。
心無い言動に心悩まされることなく、治療に専念、日々の生活を取り戻すことに専念できます。
✅ 手続き負担の軽減
後遺障害等級認定手続きや、加害者との代理交渉、裁判手続きを全てまかせることができます。
✅ 適切な後遺障害等級の認定
加害者側に対する損害賠償請求の前提となる後遺障害等級認定について、弁護士によるサポートを受けることができます。
症状に応じた適切な等級認定を受けることで、適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。
弁護士に依頼すると、一連の手続きに要する着手金や成功報酬金が高額になることがあります。
しかし、弁護士特約があれば多くの場合これらの費用を保険会社が負担してくれるため、実質的に自己負担をゼロに近づけられます。
特約利用で弁護士費用300万円までがカバーされるため、賠償金総額が1500万円を超えるような重大な交通事故まで自己負担ゼロになる可能性があります。
また、別々の保険会社で弁護士費用特約を付けていた場合、1つの事故で2つの特約を利用できる場合があります。
夫婦それぞれが加入する自動車保険に弁護士特約がついている場合で、一方が交通事故被害に遭ったときには、2社の特約を利用できます。
弁護士特約を上手に利用することで費用倒れのリスクを極力抑えながら、専門家である弁護士に相談・依頼できるのは大きな安心材料です。
保険会社が提示する示談金は、自賠責保険の基準や任意保険会社の基準に基づいて算出されることが多く、弁護士が用いる裁判の基準(弁護士基準/裁判基準)に比べて低い傾向にあります。
弁護士基準は、被害者にとって一番有利な慰謝料の相場と言えます。
弁護士に依頼することで、この弁護士基準に基づいた正当な賠償額を主張し、増額できる可能性が高まります。
特に慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など)や休業損害などで差が出やすいです。
事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合、その後遺障害等級によって受け取れる賠償金額が大きく変わります。
適切な等級認定を受けるためには、医学的な知識や提出書類に関する専門知識が必要です。
弁護士は、適切な検査や医師への働きかけ、書類の準備など、後遺障害等級認定に向けたサポートを行い、適正な等級獲得が期待できます。
交通事故では、過失割合という問題がとても重要です。
双方にどの程度の過失があったかを示す「過失割合」が変わると、最終的に受け取れる賠償金額に大きく影響します。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合でも、個人でこれを覆すのは困難です。
弁護士は、事故状況の詳細な分析や過去の判例に基づき、適正な過失割合を主張し、過失割合の修正に努めてくれます。
事故後、被害者は加害者側の保険会社との煩雑なやり取りなどをおこなう必要があります。
弁護士に依頼すれば、加害者側の心ない言動に悩まされることなく、心身的な負担を大幅に軽減できる点も大きな魅力です。
また、示談交渉だけでなく、交通事故証明書の取得、診断書や診療報酬明細書の確認、後遺障害診断書の準備、各種書類作成や申請など、交通事故に関わる様々な手続きを弁護士が代行してくれます。
示談交渉を全て弁護士に一任できるため、被害者の方は治療に専念したり、日常生活を立て直したりすることに集中できます。
弁護士特約を使用しても、任意保険の等級が下がったり翌年の保険料が上がったりすることは通常ありません。
保険料アップの心配がない点も、弁護士特約のメリットとして重視される理由の一つでしょう。
メリットが大きい弁護士特約ですが、加入や利用に際して注意すべきデメリットも存在します。代表的な懸念点を見ていきましょう。
弁護士特約は費用の面で大きなメリットがある一方、どの事故でも自由に使えるわけではありません。契約内容によっては使えないケースがあります。
また、利用時には一定の手間が生じる点も押さえておくべきです。
一般的に弁護士特約を利用しても等級が下がる・保険料が上がることはありません。
ただし、特約を付帯することでベースの保険料自体が上乗せされます。
ただ、年間2,000円~5,000円程度と低額であり、事故時の弁護士費用の支払い金額と比較した際の負担は大きくないと言えます。
弁護士費用特約を契約している保険会社から、提携している弁護士を紹介してもらうこともできますが相性の問題があります。他方、自分で弁護士を探したい場合はその手間と時間がかかります。
交通事故被害について、無料法律相談を実施している法律事務所は多くあります。
無料相談や弁護士特約を利用して、いくつか法律事務所を回って、解決実績(解決事例)が豊富か、親切丁寧かなどを確認しておくと良いでしょう。
なお、依頼後も定期的にやり取りを行う必要があり、スケジュール調整や打ち合わせが増える可能性があります。弁護士との意思疎通を丁寧に行わないと、思わぬ連絡ミスやトラブルが起こるリスクもあるため注意が必要です。
契約者が加害者となった事故や、保険の対象外となる車両を使用していたときなど、弁護士特約が適用されない場合もあります。
また、親族間の賠償問題や故意・重大な過失があるような事案に関しては補償対象外となることが多いです。
補償対象かどうか分からないときは、可能な限り早めに保険会社や弁護士へ確認するようにしましょう。
弁護士特約には一定の条件や除外規定が設けられていることがあります。
ここでは、一般的に適用されないことが多いケースを詳しく見ていきます。
特約を十分に活用するためには、どのような事故が対象となり、どのような事故が対象外になるのかを理解しておくことが大切です。
ここで挙げるケースに該当すると、弁護士費用特約を使えない可能性が高くなります。
契約時の確認はもちろん、事故後にすぐ保険会社へ問い合わせるようにしましょう。
飲酒運転や危険運転など、故意・重大な過失によって引き起こされた事故は、保険の対象外とされることが一般的です。
このような事故における弁護士特約は、保険会社の約款で除外規定に該当するため、実質的に利用できません。
台風や噴火、地震など自然災害による被害は、自動車保険そのものがカバーしないケースがあります。
弁護士特約もそれらの自然災害に起因する事故や損害賠償請求は補償対象外とされる可能性が高いです。
火災保険や地震保険など、別の保険で対応が必要になる場合があるので、保険の種類ごとの補償範囲をチェックしておきましょう。
弁護士特約は主に個人契約の自家用車を対象とすることが多く、法人名義の事業用車両は補償範囲外になることがあります。
自転車同士の事故についても特約が適用されない場合があり、保険商品や契約内容次第で大きく扱いが変わります。
仕事で使う車の場合は業務用保険を検討するなど、自身の生活環境に合わせた保険選びが重要です。
なお、法人名義の事業用車両にかかる自動車保険に弁護士費用特約を付帯できる商品もありますが、個人契約の特約と比較すると、以下のような違いや制限がある場合があります。
弁護士特約の活用で、示談交渉や費用負担の軽減に大きく役立つ場面が多々あります。
ここでは、特に利用を検討すべき状況を紹介します。
弁護士特約をどのような場面で活用すれば効果的なのかを把握しておくと、いざというときにスムーズに動けます。
特に相手方の保険状況や過失割合に争いがある場合は、早い段階で弁護士の意見を取り入れておくことが望ましいでしょう。
結果的に、より良い条件で示談が成立する可能性が高まります。
弁護士費用特約をご契約の被保険者の方が、被害者であり、かつご自身に過失が全くない、いわゆる「もらい事故」(過失割合が10対0で、被害者側が0の場合)に遭われたケースは、まさに弁護士費用特約の利用が非常に有効となる典型的な例です。
このような「もらい事故」の場合、被害者ご自身の加入している保険会社は、任意保険に付帯された示談代行サービスが利用できないことがあります。
これは、保険会社が被害者に代わって加害者側と直接交渉をおこなうことが、弁護士法第72条に抵触する(非弁行為となる)ためです。
そのため、被害者の方はご自身で加害者側やその保険会社と交渉を行う必要が出てきます。
しかし、保険会社の担当者は交渉のプロであり、個人で対等に交渉を進めるのは非常に困難で、精神的なストレスも大きくなります。
ここで弁護士費用特約が役立ちます。特約を利用することで、被害者の方は自己負担なく弁護士に交渉を依頼することができます(特約の上限金額の範囲内)。
弁護士は、被害者に代わって加害者側保険会社と専門的な知識に基づいて交渉を行います。
したがって、被害者に過失が全くない「もらい事故」は、弁護士費用特約の存在意義が特に発揮されるケースと言えます。
特約に加入している場合は、積極的に利用を検討すべき状況です。
相手側が任意保険に未加入の場合、保険会社同士の交渉が存在しないため、直接加害者とやり取りを行わなければならないケースが多くなります。
話し合いがまとまらず感情的になってしまう恐れもあり、時間と労力を要することが少なくありません。
また、加害者に支払い能力がない場合、いくら高額な賠償額で合意しても、実際に回収できなければ意味がありません。
今後の対応について、弁護士特約を利用して相談を受けるのも良いでしょう。
交通事故の加害者が保険に未加入であった場合、被害者の方が適切な賠償を受けるためには、状況に応じた対応が必要です。
加害者の保険加入状況が「自賠責保険・任意保険ともに未加入」の場合と「自賠責保険には加入しているが任意保険は未加入」の場合に分けて、それぞれの対処法を検討することになります。
― 加害者本人への直接請求
損害賠償は本来加害者が行うべきものであるため、まずは加害者本人に直接請求を行います。
しかし、保険にすら加入していない相手に十分な支払い能力があるとは限らず、交渉に応じてもらえない、支払いを滞納されるなどのリスクが高いです。
内容証明郵便を送付して請求の意思を明確にしたり、示談書を公正証書にして強制執行しやすくする、あるいは最終的に訴訟を提起し、判決に基づいて財産を差し押さえるといった法的手続きが必要になる可能性があります。
― 政府保障事業への請求
加害者が不明である場合や、加害者が自賠責保険に加入しておらず十分な賠償が得られない場合に、国が被害者に対して最低限の救済を行う制度です。
自賠責保険の支払基準に準じた額が支払われますが、治療費や休業損害、逸失利益などが対象で、物損は含まれません。
― ご自身の保険の利用
ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」が付帯されていれば、ご自身の保険から保険金を受け取ることができます。
また、「無保険車傷害特 約」が付帯されていれば、本来加害者の任意保険から支払われるべき対人賠償に相当する損害について、ご自身の保険会社に請求できる場合があります。
― 労災保険の利用
交通事故が業務中や通勤中に発生した場合は、労災保険を利用できます。
この場合、人身に関する損害については、加害者の自賠責保険に対して「被害者請求」を行うことができます。
自賠責保険は被害者保護のための最低限の補償を行うものであり、傷害による損害については上限120万円、後遺障害による損害は等級に応じて、死亡による損害は上限3000万円といった支払限度額があります。
― 加害者の自賠責保険への被害者請求
被害者が加害者の自賠責保険会社に対し、直接保険金を請求する手続きです。これにより、自賠責保険の範囲内で最低限の補償を受けることができます。必要書類を揃えて、加害者の加入している自賠責保険会社に提出します。
― 自賠責保険の限度額を超える損害への対応
自賠責保険の支払限度額を超える損害(治療費が高額になった場合、自賠責保険基準以上の慰謝料、休業損害、逸失利益、物損など)については、加害者本人に直接請求する必要があります。ここでの交渉や手続きは、上記の「① 加害者が自賠責保険・任意保険ともに未加入の場合」の加害者本人への直接請求と同様の困難が伴う可能性があります。
― ご自身の保険の利用
「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害特約」などが利用可能です。特に無保険車傷害特約は、加害者が任意保険に未加入の場合に有効な補償となることがあります。
― 労災保険の利用
①の場合と同様に利用を検討します。
上記対処法のほかに、加害者以外に賠償請求できるケースがあります。
例えば、加害者が業務中に起こした事故の場合には使用者である会社があります。
加害者本人に資力がない場合でも、勤務先である使用者や車両の管理をしている運行供用者に賠償請求をおこなうことで、少しでも被害を回復できる可能性があります。
相手方や保険会社の提示する損害賠償金額や過失割合が納得できない場合は、弁護士の知見が非常に有効です。
示談交渉において法的根拠を示すことで、より高い慰謝料や適切な過失割合を主張できる可能性があります。
感情的な部分を切り離して冷静に交渉を進めるうえでも、第三者の専門家に依頼することは有効な手段です。
事故による賠償額が小さく、弁護士費用のほうが高くついてしまう“費用倒れ”を懸念する場合でも、弁護士特約であれば負担を最小限に抑えられます。
通常の依頼であれば検討を断念するような軽微な事故でも、特約を使うことで遠慮なく専門家の力を借りることが可能となるでしょう。
小さな損害ほど迅速な対応が結果的にトラブルの長期化を防ぎ、精神的な負担を軽減します。
いざ弁護士特約を利用しようと思っても、どのような手順ですすめれば良いのでしょうか。
ここでは一般的な流れをまとめました。
事故が発生したら、まずは保険会社に連絡を行うことが基本です。
その際に弁護士特約の使用を希望する旨を伝え、実際にどのような書類が必要なのかを確認しましょう。
弁護士探しや契約手続きは保険会社が紹介する弁護士を利用するか、自身で信頼できる専門家を見つけるかで大きく段取りが異なります。
最初にすべきことは、自身の保険証券や約款をしっかり読み込み、弁護士費用特約の有無や補償額の上限、適用範囲などを再確認することです。
特に契約してから時間が経っていたり、複数の保険に加入していたりする場合は、どの契約に弁護士特約が付帯されているかを見落としがちです。
事故発生時にあわてないためにも、平時から書類を整理しておく習慣をつけると良いでしょう。
この時、同居する親族や、被害者の方が実家を出て未婚の場合には実家の親族の保険契約も必ず確認するようにしましょう。
事故対応の際、保険会社へ連絡するときに、弁護士費用特約を利用したい旨をきちんと伝えましょう。
保険会社によっては専任の担当部署があり、特約利用の手順や必要書類を案内してくれます。
連絡せずに独自に弁護士を雇うと、後になってから実は利用できないケースに該当していたり、特約が認められない可能性もあるので、事前相談は必須と言えます。
弁護士特約の保険会社が提携している弁護士事務所に依頼すれば、弁護士探しの手間が省けて楽です。
もっとも、弁護士との相性などの問題もあるので、保険会社の紹介であれば大丈夫とは限りません。
自分で弁護士を探すことも可能で、その際は過去の実績や費用、得意分野を確認すると安心です。
また、交通事故を多く取り扱っている弁護士事務所であれば、弁護士特約を利用してもスムーズに対応してもらえます。
弁護士との相性は大切なので、初回相談時にしっかりと話をしてから正式契約に進みましょう。
弁護士との契約が成立すると、被害者に代わり示談交渉や書類作成、医療記録や証拠書類を収集し、賠償金増額のためのサポートをおこないます。
弁護士費用の精算は弁護士特約の保険会社と直接おこなうため、被保険者が費用面を心配する手間は比較的少ないと言えるでしょう。
保険会社によっては示談交渉を早期に終わらせたい、弁護士への支払いをしたくないなどの理由から、弁護士特約の利用を積極的にすすめない場合があります。
なお、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるような場面での、より具体的で詳しい対処法については次のコラムで解説しています。
保険会社によっては、小規模の損害や被害金額が少額ない事案で弁護士を介入させると、交渉期間が長引くなどの理由から非協力的な態度を示す場合があります。
また、事故当初に弁護士を入れることへの抵抗感を示す担当者に出会うこともないとは言い切れません。
こうした場合でも、保険会社の言い分に左右されてはいけません。
約款上弁護士特約を利用できる権利があれば、「弁護士に依頼をすることに大きなメリットがある」ケースは多いため、示談前に一度相談することをおすすめします。
示談交渉が比較的簡単に進むと判断されたケースや、保険会社側で示談代行ができるとみなされたケースでは、わざわざ弁護士に依頼しなくても良いのではという姿勢を示されることがあります。
しかし、依頼者としては納得がいかない条件が提示されたり、交渉が一方的に進められたりする可能性があります。
最終的に弁護士特約を利用するかは契約者が判断できるため、保険会社の意向だけに流される必要はありません。
保険会社に弁護士特約の利用を渋られたり、はっきり断られたりした場合は、保険契約書や約款を再確認し、特約に基づく正当な権利であることを主張しましょう。
納得がいかない場合には、弁護士に相談を受けるのも一つの方法です。
弁護士特約利用による弁護士への依頼には、費用負担やストレス軽減など、多くのメリットがある一方で、契約時の保険料の支払いが増えたり、利用条件に注意すべき側面も存在します。
自身の状況や保険契約を総合的に考慮したうえで、賢く活用することが大切です。
加入や利用の前後で、特約の使える範囲や保険会社側の対応、弁護士とのやり取りなどを正しく把握しておくほど、いざというときにスムーズに動けるでしょう。
古山綜合法律事務所は、被害者側専門・全国対応で最適な解決のためのサポートをおこなっています。
保険会社側の元代理人弁護士が在籍しており、保険会社の仕組みを熟知しているため、賠償金増額について強みを持っています。
弁護士基準による加害者側の保険会社との交渉、後遺障害等級認定の申請などを代行いたします。
交通事故直後、通院・治療中など、どのタイミングからでも無料相談が可能です。
ぜひ解決実績豊富な古山綜合法律事務所まで、まずはご相談ください。
初回無料法律相談では、交通事故被害者の方にとって難しい示談案の診断(適正金額はいくらか)、後遺障害等級の見立て(等級認定の獲得の可能性)、過失割合のチェックなどについて実施しています。
ご事情やご状況に応じて、具体的な解決アドバイスをおこなっています。
ぜひお気軽に、そのご不安をご相談ください。
もちろん弁護士費用特約のご利用も可能です。
まずは電話やWEBフォーム(メール)、LINEからお気軽にお問い合わせください。
 072-800-1522
072-800-1522
また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。